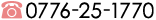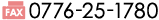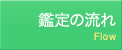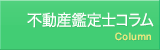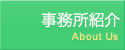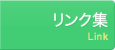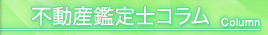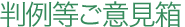1.判決の概要
本年7月15日最高裁第2小法廷において、更新料に関する判決が出された。
第1審の京都地裁、第2審の大阪高裁では、いずれも更新料は消費者契約法第10条に反して無効である旨判示され、画期的な判決として注目を集めており、その他でも下級審では無効とする判決が相次いでいた。
ところが、上記最高裁判決は、従来の流れを真っ向から否定した。
(1)更新料の意義
「更新料は,期間が満了し,賃貸借契約を更新する際に,賃借人と賃貸人との間で授受される金員である。これがいかなる性質を有するかは,賃貸借契約成立前後の当事者双方の事情,更新料条項が成立するに至った経緯その他諸般の事情を総合考量し,具体的事実関係に即して判断されるべきであるが(最高裁昭和58年(オ)第1289号同59年4月20日第二小法廷判決・民集38巻6号610頁参照),更新料は,賃料と共に賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが通常であり,その支払により賃借人は円満に物件の使用を継続することができることからすると,更新料は,一般に,賃料の補充ないし前払,賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解するのが相当である。
(2)更新料の法的適合性
「更新料条項についてみると,更新料が,一般に,賃料の補充ないし前払,賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するところであり,更新料の支払にはおよそ経済的合理性がないなどということはできない。また,一定の地域において,期間満了の際,賃借人が賃貸人に対し更新料の支払をする例が少なからず存することは公知であることや,従前,裁判上の和解手続等においても,更新料条項は公序良俗に反するなどとして,これを当然に無効とする取扱いがされてこなかったことは裁判所に顕著であることからすると,更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され,賃借人と賃貸人との間に更新料の支払に関する明確な合意が成立している場合に,賃借人と賃貸人との間に,更新料条項に関する情報の質及び量並びに交渉力について,看過し得ないほどの格差が存するとみることもできない。そうすると,賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である。
(3)上記解釈の本件への適用
これを本件についてみると,前記認定事実によれば,本件条項は本件契約書に一義的かつ明確に記載されているところ,その内容は,更新料の額を賃料の2か月分とし,本件賃貸借契約が更新される期間を1年間とするものであって,上記特段の事情が存するとはいえず,これを消費者契約法10条により無効とすることはできない。また,これまで説示したところによれば,本件条項を,借地借家法30条にいう同法第3章第1節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものということもできない。
2.今後の賃貸借契約に及ぼす影響
京都における更新料の慣行は全国でも最悪といわれており、同じ関西の大阪の人から見ても京都は家賃も高いし、更新料の取り方が異常と言われていることを最高裁の判事の方々はどこまで理解していたのであろうか。
1年間で家賃の2か月分の更新料ということは、京都は1年が14ヵ月あるということであり、更新料がない場合と比較して1カ月当たり約16.7%も家賃が高いということである。
例えば、関東圏(東京)であれば更新料は2年間で月額賃料の1カ月分程度であり、更新料がない場合と比較すると1カ月当たり約4.2%高いだけである。また、不動産業者によっては更新手数料ということで家賃の半月分程度未満しか取らない場合もある。
この背景には京都の賃貸物件を取り巻く特殊な市場環境が色濃く反映していると言われている。それは京都の大学(短大・専門学校等を含む)の多さであり、毎年3月には膨大な賃貸需要が極めて短期間のうちに発生し、圧倒的な貸し手市場と化してしまい、大学に通うために直ぐに決めなければならない新入生とその家族は止む無く貸し手の言いなりに契約を締結させられているのである。
そういった特殊な状況の中で一筋の光明が見えたのが平成21年9月25日の京都地裁での判決であり、あの判決によりその翌月から更新料を取り交わしていた既存の物件にまで更新料の減額が及んだことを見ても、貸し手側が賃料を取り過ぎていたことに対して引け目を感じていたことの裏返しの反応に見えるのは私だけであろうか。
1年で2ヶ月の更新料が特段の事情があるとはいえないという国民目線(庶民感覚)からあまりにも乖離した今回の判決、その今後に及ぼす影響は大きいといわざるを得ないが、不動産市場とそれを取り巻く環境も時々刻々変化しており、今回の判決の賞味期限は意外と早めに訪れるかもしれない。