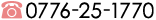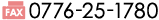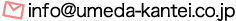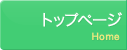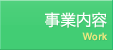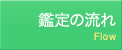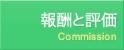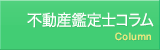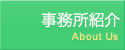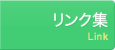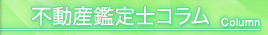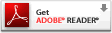更新料に関して相次ぐ最高裁判例
1.判決の概要 本年7月15日最高裁第2小法廷において、更新料に関する判決が出された。 第1審の京都地裁、第2審の大阪高裁では、いずれも更新料は消費者契約法第10条に反して無効である旨判示され、画期的な判決として注目を集めており、その他でも下級審では無効とする判決が相次いでいた。 ところが、上記最高裁判決は、従来の流れを真っ向から否定した。 (1)更新料の意義 「更新料は,期間が満了し,賃貸借契約を更新する際に,賃借人と賃貸人との間で授受される金員である。これがいかなる性質を有するかは,賃貸借契約成立前後の当事者双方の事情,更新料条項が成立するに至った経緯その他諸般の事情を総合考量し,具体的事実関係に即して判断されるべきであるが(最高裁昭和58年(オ)第1289号同59年4月20日第二小法廷判決・民集38巻6号610頁参照),更新料は,賃料と共に賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが通常であり,その支払により賃借人は円満に物件の使用を継続することができることからすると,更新料は,一般に,賃料の補充ないし前払,賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解するのが相当である。 (2)更新料の法的適合性 「更新料条項についてみると,更新料が,一般に,賃料の補充ないし前払,賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するところであり,更新料の支払にはおよそ経済的合理性がないなどということはできない。また,一定の地域において,期間満了の際,賃借人が賃貸人に対し更新料の支払をする例が少なからず存することは公知であることや,従前,裁判上の和解手続等においても,更新料条項は公序良俗に反するなどとして,これを当然に無効とする取扱いがされてこなかったことは裁判所に顕著であることからすると,更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され,賃借人と賃貸人との間に更新料の支払に関する明確な合意が成立している場合に,賃借人と賃貸人との間に,更新料条項に関する情報の質及び量並びに交渉力について,看過し得ないほどの格差が存するとみることもできない。そうすると,賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である。 (3)上記解釈の本件への適用 これを本件についてみると,前記認定事実によれば,本件条項は本件契約書に一義的かつ明確に記載されているところ,その内容は,更新料の額を賃料の2か月分とし,本件賃貸借契約が更新される期間を1年間とするものであって,上記特段の事情が存するとはいえず,これを消費者契約法10条により無効とすることはできない。また,これまで説示したところによれば,本件条項を,借地借家法30条にいう同法第3章第1節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものということもできない。 2.今後の賃貸借契約に及ぼす影響 京都における更新料の慣行は全国でも最悪といわれており、同じ関西の大阪の人から見ても京都は家賃も高いし、更新料の取り方が異常と言われていることを最高裁の判事の方々はどこまで理解していたのであろうか。 1年間で家賃の2か月分の更新料ということは、京都は1年が14ヵ月あるということであり、更新料がない場合と比較して1カ月当たり約16.7%も家賃が高いということである。 例えば、関東圏(東京)であれば更新料は2年間で月額賃料の1カ月分程度であり、更新料がない場合と比較すると1カ月当たり約4.2%高いだけである。また、不動産業者によっては更新手数料ということで家賃の半月分程度未満しか取らない場合もある。 この背景には京都の賃貸物件を取り巻く特殊な市場環境が色濃く反映していると言われている。それは京都の大学(短大・専門学校等を含む)の多さであり、毎年3月には膨大な賃貸需要が極めて短期間のうちに発生し、圧倒的な貸し手市場と化してしまい、大学に通うために直ぐに決めなければならない新入生とその家族は止む無く貸し手の言いなりに契約を締結させられているのである。 そういった特殊な状況の中で一筋の光明が見えたのが平成21年9月25日の京都地裁での判決であり、あの判決によりその翌月から更新料を取り交わしていた既存の物件にまで更新料の減額が及んだことを見ても、貸し手側が賃料を取り過ぎていたことに対して引け目を感じていたことの裏返しの反応に見えるのは私だけであろうか。 1年で2ヶ月の更新料が特段の事情があるとはいえないという国民目線(庶民感覚)からあまりにも乖離した今回の判決、その今後に及ぼす影響は大きいといわざるを得ないが、不動産市場とそれを取り巻く環境も時々刻々変化しており、今回の判決の賞味期限は意外と早めに訪れるかもしれない。
東日本大震災を考える(鑑定士からの視点)その1
東日本大震災から早くも1カ月が経過しました。この間度重なる余震活動に耐えながら被災地の方々は懸命に立ち上がろうとされていることに心より敬意とエールを送りたいと思います。 この度の地殻変動が引き起こした影響は国民経済に計り知れない影響を与えており、今後も与え続けると思われますが、不動産の経済価値にどのような影響を与えていくのか考えずにはおれません。 今この時期にコメントすることが不適切の謗りを受けるかもしれませんが、様々な角度から検討してみたいと思います。 (1)建物の耐震性の問題 一度でも震度5以上の強い地震を経験した建物とそうでない建物が同じ強度を保てるのかという問題があります。 東京都区部でも震度5強を観測したわけですが、古いビルであれ新しいビルであれ、外見上何も変らなくても建物は相当なダメージを受けているのではないかと思われます。 そうなると設計上の耐震強度を引続き維持できているかどうかという検証を行う必要はないのか、行わない場合に震度5強の地震を経験した建物について、全く地震の影響がないという前提で捉えて良いのかということに対して、国、特に国土交通省及び建設業界は応える必要があるのではないでしょうか。 (2)岩手・仙台・福島の地盤にズレが生じたエリアの建物の再建築について 牡鹿半島で東南東に5.3m程度移動し、約1.2m沈下しており、東北の太平洋沿岸はいずれの場所も多少の差はあれメートル単位で土地が移動しています。 今後の復興のなかで、各種建物の再建築を行っていくうえで、どこに建て直すかという点について、相当な調査と整理が必要と思われます。 移動したのが一部のエリアではなく日本列島そのものが移動しているので、既存の境界標がベースとなってくると思われますが、各種交通インフラの再建設の過程において、仮に元通りの場所に道路・鉄道・水路等を復元したとしても元々あった土地に収まるという保証はありません。 何故なら、今後の安全性を考慮して、道路を拡幅したり、通る位置をずらしたりということが現実には起きてくるからです。 また、今回の震災と津波で壊滅的な被害にあった地区は大体的な都市計画により再開発が進むものと思われるが、被害が壊滅的でなく家屋が全半壊程度で残った地区は被災者の思い出が残っており、直ぐの取壊して撤去することが困難な状況にあります。 今後ともさらにこのテーマについては、逐次コメントを追加してまいります。
賃貸等不動産の価格調査における東日本大震災の評価上の取扱い
あまりにも甚大な被害のため今回の震災が不動産の経済価値にどのような影響を与えるかは現段階では計り知れないものの、鑑定評価は時々刻々と行なっていかなければなりません、 当面の対応として我々の所属団体である社団法人不動産鑑定協会より別添の文書が発分されました。 ポイントとしては、当面の間価格形成要因から除外することを可能にするものであります。 東日本大震災評価上の取扱い (社団法人不動産鑑定協会のHP http://www.fudousan-kanteishi.or.jp/)
工場抵当法とは?-その2
4.工場財団の意義 工場財団とは、工場企業を構成する物的設備及び権利を一体として抵当権の目的とするために設定される財団である。 工場財団は、工場財団登記記録に所有権保存登記を行うことによって創設され、一個の不動産とみなされる。 したがって、いったん工場財団として創設されると、本来不動産ではない機械・器具等も民法上は不動産として取り扱われることになる。 但し、工場財団を目的とする権利設定は、所有権と抵当権に限定される。 5.工場財団の設定 (1)工場財団組成物件 工場財団は、次に掲げる客体の全部若しくは一部を持って構成される。 ①工場に属する土地 ②工作物(建物・橋梁・塀・用水タンク・原材料貯蔵所・寄宿舎等を含む) ③機械、器具(車両・船舶・運搬具等を含む) ④電柱、電線 ⑤各種埋設管(水道・下水道・ガス・井戸・融雪装置) ⑥軌条その他の付属物(工場の用に供する付属の動産) ⑦地上権・賃貸人の承諾のある賃借権・工業所有権・ダム使用権等 上記の中での構成は自由であるが、土地・建物の所有権、土地・建物の利用権は必ず含めなければならない反面、機械・器具等を入れないで、単純に不動産だけで財団を組成することも可能である。 (2)工場財団組成物件の成立要件 工場財団には、他人の権利の目的となっているもの、差押、仮差押、仮処分の目的となっているものを含めることは出来ない。 不動産については、登記されたものしか財団を組成できないので明らかな反面、動産については公示方法がないので、一定期間の権利の申出期間の公告を行ったうえで、申出がない権利については存しないものとして取り扱うことになる。 権利がないものとして扱われるのは、工場財団抵当権が存続する限りにおいてだけであり、工場財団抵当権が消滅すれば、原権利者の権利は回復する。 工場財団組成物件の動産に関する組成時における不備と財団組成の煩雑さを回避する一つの手段として、動産譲渡登記制度が創設された。 (3)動産譲渡登記制度の概要 平成16年11月25日に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、平成17年10月3日から動産譲渡登記制度の運用が開始された。 この制度を利用して行われた動産の所有権移転に関して、動産譲渡登記がなされると、当該動産について、民法第178条の引渡しがあったものとみなされ、対抗要件が具備されることになる。 この制度を利用することで工場財団抵当よりも簡便に動産を一括して抵当の目的とすることが可能である。 http://www.moj.go.jp/MINJI/DOUSANTOUKI/seido.html
工場抵当法とは?-その1
1.工場抵当法の意義 工場は、土地・建物・機械器具等の設備が有機的に結合して効用を発揮するものであり、個別の資産に分解しては全体で発揮している効用に及ばないこととなる。 工場を担保として設定する場合や企業の継続価値を計る上でも同じことが言えるので、工場に帰属する不動産と動産を総体として担保権を設定する法理論として財団抵当制度が必要となり、それを具体化したものが工場抵当法である。 2.工場抵当法の種類 一つは広義の工場抵当である工場財団抵当である。 これは工場の土地・建物に備付けた機械・器具その他工場の用に供する物について目録を作成し、これを一つの財団として抵当権を設定するものである(工場抵当法第3条)。 もう一つは狭義の工場抵当と言われるものである。 工場財団抵当と異なり、財団を組成しないで、機械・器具等を不動産と共に抵当の目的とする制度である(工場抵当法第2条)。 3.工場抵当法上の工場の定義 工場抵当法では、同法第1条で「営業のため物品の製造若しくは加工又は印刷若しくは撮影の目的に使用する場所をいう」とされる。 具体例を挙げると、次のとおりである。 (1)水産物冷蔵庫に付随する土地・建物・機械・器具等は一体として工場財団を組成可能である。 (2)映画館は工場ではない。 (3)ガソリンスタンドは工場ではない。 (4)油槽所は工場に該当する。 (5)給食施設は工場に該当する。
改正土壌汚染対策法の概要
平成22年4月1日より改正された土壌汚染対策法が施行された。平成15年4月に施行されてから初めての大改正である。 続きを読む
借地借家法による賃料増減額請求権とは
土地の地代や建物の家賃について契約当事者で話し合いが付かない場合に借主・貸主双方から請求し得る権利として規定されている。 続きを読む
現在執筆中
この記事は現在執筆中です。 もうしばらくお待ち下さい。
留置権の法的効果について
民事留置権とは,物の留置を認めることによって,その物の返還を求めようとする債務者を間接的に強制して債務の弁済を担保するもの・・・ 続きを読む